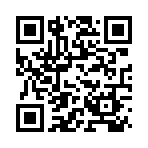2008年11月18日
Hi-Capa5.1⑧
こんばんは。VUELTAです。
今回は、スライドストップの加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
例によって、写真を1枚。

もう見飽きた、ピンボケ。許されざる物とは、知ってはいても、これしか写真がないのよ。お許し下さい。
ほんで、どっか変わったのかい?
はい。セレーションのところを、ゴムヤスリで、磨きました。いい感じに、鈍い光があります。使い込んだ光り方?見たいな感じです。それらしい感じで、鈍く光ります。結構、お勧めです。
もう1枚。

ちゃんと、突っ立ってくれないので、六角レンチに介添えしてもらってます。
また、例によって、穴開けました。大きさを変えて、2発!その後、リーマーで、角を浚いました。側面は、磨いてないので、2トンカラーのような、アクセントになりました。これも、組んでみると、いい感じ。お気に入りです。
実は写真がないのですが、もう1箇所、穴あけしてあります。1枚目の写真で、気がついた人は、かなりの人。完全にヲタ系を自任できる人でしょう。写真では、一番上、アウターバレルを固定するシャフト部分、掘り込みました。まっすぐ開けるのが、心配でしたが、まぁ、なんとかなったでしょう。貫通させれば、かなり軽く出来るでしょうが、やり過ぎると、強度が無くなるので、2/3ぐらいで止めました。適当にやりましょう。なにせ、爪の垢カスタムですから。
今回、軽量加工として、ドリルで、3箇所の肉抜きでした。重量は、6グラムでした。
以上、スライドストップの加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
今回は、スライドストップの加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
例によって、写真を1枚。

もう見飽きた、ピンボケ。許されざる物とは、知ってはいても、これしか写真がないのよ。お許し下さい。
ほんで、どっか変わったのかい?
はい。セレーションのところを、ゴムヤスリで、磨きました。いい感じに、鈍い光があります。使い込んだ光り方?見たいな感じです。それらしい感じで、鈍く光ります。結構、お勧めです。
もう1枚。

ちゃんと、突っ立ってくれないので、六角レンチに介添えしてもらってます。
また、例によって、穴開けました。大きさを変えて、2発!その後、リーマーで、角を浚いました。側面は、磨いてないので、2トンカラーのような、アクセントになりました。これも、組んでみると、いい感じ。お気に入りです。
実は写真がないのですが、もう1箇所、穴あけしてあります。1枚目の写真で、気がついた人は、かなりの人。完全にヲタ系を自任できる人でしょう。写真では、一番上、アウターバレルを固定するシャフト部分、掘り込みました。まっすぐ開けるのが、心配でしたが、まぁ、なんとかなったでしょう。貫通させれば、かなり軽く出来るでしょうが、やり過ぎると、強度が無くなるので、2/3ぐらいで止めました。適当にやりましょう。なにせ、爪の垢カスタムですから。
今回、軽量加工として、ドリルで、3箇所の肉抜きでした。重量は、6グラムでした。
以上、スライドストップの加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
2008年11月14日
Hi-Capa5.1⑦
こんばんは。VUELTAです。
今回は、グリップセーフティの加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
さっき、BLOGをUPしようとしたら、全部消えてしもうた!なぁんてこったぃ!
今までに、かれこれ5回は、失敗しとる!情けなや!!!!
さて、気を取り直して、
例によって、写真を1枚。

はい。なぁ~んじゃ。色、変えただけかい!とか言わないでください。所詮、素人のやることですから。
今回は、下地を、軽く荒らしてから、プライマーも吹かずに、キャロムのチタニウムシルバーを、吹きつけています。面倒だったので、パーティングラインも消さずに、塗ってしまいました。この塗料は、結構なお値段ではありますが、値段なりの価値はあります。先ず、塗装が大嫌いな私でも、ちゃんと乾燥させてやれば、結構きれいに仕上がること。サッと吹きつけて、30秒ぐらいで、指乾燥と言われるぐらいに乾燥し、次の吹き付けに移れること。金属に吹きつけても、ほぼ、2・3日で乾燥すること。完全に乾燥すれば、少々当たったぐらいでは、塗装が剥がれることがない。など、3000円ほどの値打ち以上のことはあると思います。
ここで、もう1枚。

やっぱり、持ってみると重かったので、穴あけしました。
見てのとおり、パーティングラインは、消していません。上の方の線は、万力で掴みそこなったときに出来た傷です。パーティングラインと共に、消せば良かったのですが、本当に面倒くさがりですので、今後の戒めとして、そのままにしておきました。そのうち、再加工するかもしれませんが、しばらく、このままです。この穴ですが、リズム感というか、変化のようなものが欲しかったので、上から順に、8ミリ・7ミリ・6ミリと、大きさを変えてあります。穴あけの後、軽く面取りを兼ねて、リーマーをかけています。当初予定では、もっと穴を開けて、軽くしてやろうと思っていたのですが、裏側に、セイフティレバーが通る穴があったり、シアーSPを押す部分があったりと、あまり、触りたくなかったので、3つに留めました。裏側から、ドリドリして、少しでも軽くする手もあったのですが、現状では、そのままです。結果的に、良い感じになったと思います。
今回、軽量加工として、ドリルで、3箇所の肉抜きと、塗装でした。重量は、24グラムでした。
以上、グリップセーフティ周辺の加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
今回は、グリップセーフティの加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
さっき、BLOGをUPしようとしたら、全部消えてしもうた!なぁんてこったぃ!
今までに、かれこれ5回は、失敗しとる!情けなや!!!!
さて、気を取り直して、
例によって、写真を1枚。

はい。なぁ~んじゃ。色、変えただけかい!とか言わないでください。所詮、素人のやることですから。
今回は、下地を、軽く荒らしてから、プライマーも吹かずに、キャロムのチタニウムシルバーを、吹きつけています。面倒だったので、パーティングラインも消さずに、塗ってしまいました。この塗料は、結構なお値段ではありますが、値段なりの価値はあります。先ず、塗装が大嫌いな私でも、ちゃんと乾燥させてやれば、結構きれいに仕上がること。サッと吹きつけて、30秒ぐらいで、指乾燥と言われるぐらいに乾燥し、次の吹き付けに移れること。金属に吹きつけても、ほぼ、2・3日で乾燥すること。完全に乾燥すれば、少々当たったぐらいでは、塗装が剥がれることがない。など、3000円ほどの値打ち以上のことはあると思います。
ここで、もう1枚。

やっぱり、持ってみると重かったので、穴あけしました。
見てのとおり、パーティングラインは、消していません。上の方の線は、万力で掴みそこなったときに出来た傷です。パーティングラインと共に、消せば良かったのですが、本当に面倒くさがりですので、今後の戒めとして、そのままにしておきました。そのうち、再加工するかもしれませんが、しばらく、このままです。この穴ですが、リズム感というか、変化のようなものが欲しかったので、上から順に、8ミリ・7ミリ・6ミリと、大きさを変えてあります。穴あけの後、軽く面取りを兼ねて、リーマーをかけています。当初予定では、もっと穴を開けて、軽くしてやろうと思っていたのですが、裏側に、セイフティレバーが通る穴があったり、シアーSPを押す部分があったりと、あまり、触りたくなかったので、3つに留めました。裏側から、ドリドリして、少しでも軽くする手もあったのですが、現状では、そのままです。結果的に、良い感じになったと思います。
今回、軽量加工として、ドリルで、3箇所の肉抜きと、塗装でした。重量は、24グラムでした。
以上、グリップセーフティ周辺の加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
2008年11月07日
Hi-Capa5.1⑥
こんばんは。VUELTAです。
今回は、ピストン周辺の加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
例によって、写真を1枚。

はい、色が違いますが、見慣れたパーツですね。東京マルイでは、ピストン・シリンダーという部品名称です。WA社のように、ブリーチとかいう名前ではありません。名称からすると、なんだが逆のような気もしますが、そんなことは置いといて、早速、加工編に入ります。
ぱっと見、色が違うだけやないか!と思われるでしょうが、ちょいと、良く見ておくんなまし。
もう1枚。

まぁた、ピンボケかい!すいません。写真がこれしかないんです。でも、どんなもんかは、分かるでしょ?スライド周りで、一番重い部品だけに、軽量化の効果は、必ずあります。バッサリ落としました。結構な軽量化です。相変わらず、ドリルで穴開けて、穴を繋げて、ヤスリで整えて、リューターで磨きました。ピッカピカになります。下面のフレームとの接触部分なんか、つるっつるです。工具は、リューター用のゴムやすりです。100均で購入しました。なかなか使えます。ホームセンターで買うよりは、使い捨てのような工具ですので、こちらで十分です。ほんとに、ピカッピカになります。顔が映るくらい。ピカピカのままですと、やがて酸化して、黒くくすんできます。ですので、手元にあった、プラモデル用ラッカー系のクリアーレッドを、塗りました。んが、組み込みの途中に、あちこち引っ掛けて、ペリペリ剥がれちゃうんです。金属のツルツルだから、足付けしなかったのが、悪かった。今度バラしたときに、塗り直しです。
さて、ここまでなら、良くある軽量化です。ついでですから、もう一歩、踏み込みましょう。
このHi-Capa5.1を弄ると決めたときに決めた、いくつかの約束事を書いておきます。
①スライドの四角い形は変えない。(やっぱり、ガバ系ですから)
②コンペンセイターをつける。(やっぱり、格好重視です)
③ショートブローバックにする。(やっぱり、リコイルは、少なめで)
④ガスの消費を抑える。(やっぱり、エコロジー)
⑤ドットサイトを乗せる。(やっぱり印象が大事)
⑥装備重量は、ノーマルの50グラムUP程度の重量増に抑えたい。(やっぱり、増えた分だけ、ダイエット)
⑦パワーアップ加工はしない。(やっぱり、ご時勢ですから)
⑧カスタムパーツは、なるべく使わない。(やっぱり、財布に優しく)
などです。
これの、①②は、以前のBLOGのとおりです。
③④が、前回と、今回のBLOGに係ってきます。
ショートストロークは、スライド等上半分だけの加工です。ガスの燃費は、上半分と、ハンマーSPなど、色んな所に手を入れねばなりません。ですので、今回は、上半分に絞って、進めます。
いろんな方の話や実験から、ガスブロの、ガスの消費の半分以上は、ブローバックに充てられている、というのが判っています。たぶん、2/3ぐらいでしょう。これを減らしたいわけです。なぜ、減らしたいのか?これは、単純に、ガス圧の安定のためです。Hi-Capaは、多分、2マガジンぐらいで撃てなくなると思います。今の季節、8連射くらいすると、初弾と終弾では、明らかに弾道が変わっているはずです。シューティングマッチで、これは、致命的です。
で、写真を、もう1枚。

はい、見飽きたピンボケ。今日、最後ですから、ご勘弁。
こんな、ボケ写真の、どこを見るんじゃい!との声が聞こえてくるようですが、下の、スライドと当たる部分、白いところがありますね。ここのところに注目!です。これは何かと申しますと、プラ板です。今は、両面テープで貼り付けてあるだけですが、支障はないので、このまま使い続けると思います。あ、いやいや、そんなことではなく、このプラ板で、ガスカットのタイミングを、早めているのです。これこそが、今回の加工の、重要ポイントです。
ガスカットのタイミングを決めているのは、ピストンの溝部分です。ガスカット自体は、部品番号H51-50ノッカーロック等がしています。で、スライド側としては、この溝を、給弾するのに必要なだけ、ブローバックさせてやるように延長加工すればいいのです。で、上の写真ほど、埋めました。もう少し埋めれるのですが、マージンを取って、このぐらいにしてあります。これは、スライドストップがかからなければダメ!というレギュレーションがある場合、リコイルSPガイドの、カラー・ゴムを外せば、その場でも、対応出来るようにするためでもあります。もう少し埋めれば、ブローバックを始めた後、ぷすんと、力尽きたように、スライドが戻ります。リコイルショックも少なく、かなり撃ちやすくなります。私個人としては、ちょっとぐらい、リコイルショックが欲しいですけど、これは、個人の考え方でしょうね。
以上、今回の、加工部分でした。
見てのとおり、シリンダー部分の加工は、一切していません。もし、するのであれば、H51-21シリンダーバルブSPを強い物にしたいかな?というところです。どうやら、この部品で、発射とブローバックのタイミングを決めているようで、これを強い物と交換すると、初速が上がるはずです。私は、現在の弾道に、不満がないので、触りませんでした。
今回、ピストンの軽量加工として、肉抜き。ショートストローク加工として、プラ板での延長。作動のスムーズ加工として、磨き。以上の加工で、38グラム。シリンダー一式加工無しで、5グラム。計43グラムです。
相変わらずの長文に、お付き合い、ありがとうございました。
以上、ピストン周辺の加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
今回は、ピストン周辺の加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
例によって、写真を1枚。

はい、色が違いますが、見慣れたパーツですね。東京マルイでは、ピストン・シリンダーという部品名称です。WA社のように、ブリーチとかいう名前ではありません。名称からすると、なんだが逆のような気もしますが、そんなことは置いといて、早速、加工編に入ります。
ぱっと見、色が違うだけやないか!と思われるでしょうが、ちょいと、良く見ておくんなまし。
もう1枚。

まぁた、ピンボケかい!すいません。写真がこれしかないんです。でも、どんなもんかは、分かるでしょ?スライド周りで、一番重い部品だけに、軽量化の効果は、必ずあります。バッサリ落としました。結構な軽量化です。相変わらず、ドリルで穴開けて、穴を繋げて、ヤスリで整えて、リューターで磨きました。ピッカピカになります。下面のフレームとの接触部分なんか、つるっつるです。工具は、リューター用のゴムやすりです。100均で購入しました。なかなか使えます。ホームセンターで買うよりは、使い捨てのような工具ですので、こちらで十分です。ほんとに、ピカッピカになります。顔が映るくらい。ピカピカのままですと、やがて酸化して、黒くくすんできます。ですので、手元にあった、プラモデル用ラッカー系のクリアーレッドを、塗りました。んが、組み込みの途中に、あちこち引っ掛けて、ペリペリ剥がれちゃうんです。金属のツルツルだから、足付けしなかったのが、悪かった。今度バラしたときに、塗り直しです。
さて、ここまでなら、良くある軽量化です。ついでですから、もう一歩、踏み込みましょう。
このHi-Capa5.1を弄ると決めたときに決めた、いくつかの約束事を書いておきます。
①スライドの四角い形は変えない。(やっぱり、ガバ系ですから)
②コンペンセイターをつける。(やっぱり、格好重視です)
③ショートブローバックにする。(やっぱり、リコイルは、少なめで)
④ガスの消費を抑える。(やっぱり、エコロジー)
⑤ドットサイトを乗せる。(やっぱり印象が大事)
⑥装備重量は、ノーマルの50グラムUP程度の重量増に抑えたい。(やっぱり、増えた分だけ、ダイエット)
⑦パワーアップ加工はしない。(やっぱり、ご時勢ですから)
⑧カスタムパーツは、なるべく使わない。(やっぱり、財布に優しく)
などです。
これの、①②は、以前のBLOGのとおりです。
③④が、前回と、今回のBLOGに係ってきます。
ショートストロークは、スライド等上半分だけの加工です。ガスの燃費は、上半分と、ハンマーSPなど、色んな所に手を入れねばなりません。ですので、今回は、上半分に絞って、進めます。
いろんな方の話や実験から、ガスブロの、ガスの消費の半分以上は、ブローバックに充てられている、というのが判っています。たぶん、2/3ぐらいでしょう。これを減らしたいわけです。なぜ、減らしたいのか?これは、単純に、ガス圧の安定のためです。Hi-Capaは、多分、2マガジンぐらいで撃てなくなると思います。今の季節、8連射くらいすると、初弾と終弾では、明らかに弾道が変わっているはずです。シューティングマッチで、これは、致命的です。
で、写真を、もう1枚。

はい、見飽きたピンボケ。今日、最後ですから、ご勘弁。
こんな、ボケ写真の、どこを見るんじゃい!との声が聞こえてくるようですが、下の、スライドと当たる部分、白いところがありますね。ここのところに注目!です。これは何かと申しますと、プラ板です。今は、両面テープで貼り付けてあるだけですが、支障はないので、このまま使い続けると思います。あ、いやいや、そんなことではなく、このプラ板で、ガスカットのタイミングを、早めているのです。これこそが、今回の加工の、重要ポイントです。
ガスカットのタイミングを決めているのは、ピストンの溝部分です。ガスカット自体は、部品番号H51-50ノッカーロック等がしています。で、スライド側としては、この溝を、給弾するのに必要なだけ、ブローバックさせてやるように延長加工すればいいのです。で、上の写真ほど、埋めました。もう少し埋めれるのですが、マージンを取って、このぐらいにしてあります。これは、スライドストップがかからなければダメ!というレギュレーションがある場合、リコイルSPガイドの、カラー・ゴムを外せば、その場でも、対応出来るようにするためでもあります。もう少し埋めれば、ブローバックを始めた後、ぷすんと、力尽きたように、スライドが戻ります。リコイルショックも少なく、かなり撃ちやすくなります。私個人としては、ちょっとぐらい、リコイルショックが欲しいですけど、これは、個人の考え方でしょうね。
以上、今回の、加工部分でした。
見てのとおり、シリンダー部分の加工は、一切していません。もし、するのであれば、H51-21シリンダーバルブSPを強い物にしたいかな?というところです。どうやら、この部品で、発射とブローバックのタイミングを決めているようで、これを強い物と交換すると、初速が上がるはずです。私は、現在の弾道に、不満がないので、触りませんでした。
今回、ピストンの軽量加工として、肉抜き。ショートストローク加工として、プラ板での延長。作動のスムーズ加工として、磨き。以上の加工で、38グラム。シリンダー一式加工無しで、5グラム。計43グラムです。
相変わらずの長文に、お付き合い、ありがとうございました。
以上、ピストン周辺の加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
2008年11月06日
Hi-Capa5.1⑤
こんばんは。VUELTAです。
今回は、リコイルプラグ周辺の加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
例によって、写真を1枚。

はい、分解したことがある人は、見慣れた部品が並んでいますね。
でも、下段の左から3つの部品は、パーツリストには載っていません。黒い円形の部品は、2ミリ厚のゴム板の切抜きです。白い部品は、ホームセンターで買ったプラ製のパイプを切ったものです。この3つの部品は、ブローバックを、強制的に約半分にするために、組み込んだ部品です。
なぜ、Hi-Capaの素晴らしいブローバックを、いちいち約半分にするのか?と言われるでしょうが、理由としては、スライドの軽量化と共に加工することによって、リコイルショックを減らせる、というのが一つ。ブローバック開始から終了までの時間を短くできる。などの、メリットがあるといわれています。では、デメリットは?といいますと、まず、どっしりとしたリコイルショックが半減される、もう一つ大事なことは、スライドの後退不足による、BB弾の装填不良が出る可能性がある、ということでしょう。後者だけは、避けなくてはなりません。弾の出ないエアソフトガンなんて、クリープを入れない・・・、いやいや、年齢がバレてしまいますね。シューティングマッチなどに使うのであれば、点数や、タイムが全てですから、外見などどうでもよく、軽くて扱いやすいツールとしての銃が良いでしょう。しかし、トイガンとしては、また違うものになるでしょう。コレクション・触感・重量感・雰囲気などなど、いろいろ楽しめるものです。が、しかし、加工した理由の大部分は、元ネタのWA社チャンピオンシップ・カスタムの仕様が、これに似たものだった、というのが本当のところです。
さて、話は戻ります。
私は、先の3つの部品を組み込んで、ブローバックさせたとき、スライドストップが組み込めるギリギリの長さに調整しています。まず、ゴムリングを1つ、スプリングガイドに入れ、そのあとに、プラ製のカラー、また、ゴムリングという順のあとリコイルSP・リコイルSPガイド、と組み込みました。結果、ショートストロークの効果を、十分に確認できました。私は、その他の軽量化や、ピストンの加工などを、全部一度にやってしまったため、一つ一つの加工の効果を、確認できませんでしたが、現在、全体の銃としてのバランスは、結構良いほうだと思います。そうそう、私は、入手の都合上、プラ製のパイプを使いましたが、シリコンチューブなどのほうが、部品への負担がが少なくなって、良いかもしれませんね。
また、話がそれました。加工の話でした。では、気をとりなおして写真を1枚。

あいや~、見事なピンボケですな。腕の悪さが、窺い知れます。申し訳ない。
この部品は、リコイルプラグです。マルイ純正部品の上半分を、バッサリ切り落としました。あまりやり過ぎると、リコイルSPの保持ができなくなる可能性があります。裏側の写真がありませんが、裏側も、ドリルで肉抜きしてあります。穴が貫通してしまうと、リコイルSPの動きに干渉するかもしれないので、ほどほどにしてあります。
では、もう、一枚。

これまた、ピンボケ。平にご容赦を。純正リコイルSPガイドです。どこか違うのか?といわれるでしょう。ドリルに銜えさせて、耐水ペーパーで磨きました。1000番1500番2000番の順です。その結果、まあ、どうでしょう。ピッカピカになりました。だからどうなの!とツッコミが、入るでしょう。では、ここでオマケの、もう一枚。

ま~た、ピンボケかい!エエ加減にせぃよ!。はい。これが本日最後のピンボケ写真です。
リコイルSPガイドを、正面から撮りました。実は、ガイドを持ったときに、重いなぁ、と思ったのが事の起こりです。じゃあ、穴でも掘ったろ!と思い立ち、万力でガイドを掴み、1ミリのドリルでドリドリしていたとき、掴みが甘く、ガイドが滑って、万力の掴み跡ができてしまいました。仕方がないので、どうせついた傷なので、しっかり掴ませて、しっかりドリドリしました。先の、ピカピカのガイドは、そんな理由からできたものでした。まぁ、結果オーライ!ということにしておきましょう。最悪、失敗しても、傷物にしてしまったスプリンガイドですから、遠慮なく、穴あけできました。
そうそう、今回、なるべく社外パーツは使わずに弄っておりますが、部品調達の都合上、ついでに買った部品がいくつかあります。その都度、載せていきますが、今回のリコイルSPは、PDI社のリコイルSP HDとなっております。これは、狙ったわけではなく、ついでに買ったものです。この製品の、うたい文句の「ソフトなテンションが ガス圧低下による冬場の作動性低下を向上。」というのが、効いているのかは判りませんが、確かに、今の状態では、ノーマルより、燃費がいい様です。
さて、また長くなりました。今回の加工で、リコイルSPガイド・31グラム。リコイルプラグ・13グラム。カラー・ゴム一式・2グラム。リコイルSP・2グラム。計48グラムとなっております。いつものように、ノーマルを量っていないのですが、まさに、爪の垢でしょうね。
以上、リコイルプラグ周辺の加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
今回は、リコイルプラグ周辺の加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
例によって、写真を1枚。

はい、分解したことがある人は、見慣れた部品が並んでいますね。
でも、下段の左から3つの部品は、パーツリストには載っていません。黒い円形の部品は、2ミリ厚のゴム板の切抜きです。白い部品は、ホームセンターで買ったプラ製のパイプを切ったものです。この3つの部品は、ブローバックを、強制的に約半分にするために、組み込んだ部品です。
なぜ、Hi-Capaの素晴らしいブローバックを、いちいち約半分にするのか?と言われるでしょうが、理由としては、スライドの軽量化と共に加工することによって、リコイルショックを減らせる、というのが一つ。ブローバック開始から終了までの時間を短くできる。などの、メリットがあるといわれています。では、デメリットは?といいますと、まず、どっしりとしたリコイルショックが半減される、もう一つ大事なことは、スライドの後退不足による、BB弾の装填不良が出る可能性がある、ということでしょう。後者だけは、避けなくてはなりません。弾の出ないエアソフトガンなんて、クリープを入れない・・・、いやいや、年齢がバレてしまいますね。シューティングマッチなどに使うのであれば、点数や、タイムが全てですから、外見などどうでもよく、軽くて扱いやすいツールとしての銃が良いでしょう。しかし、トイガンとしては、また違うものになるでしょう。コレクション・触感・重量感・雰囲気などなど、いろいろ楽しめるものです。が、しかし、加工した理由の大部分は、元ネタのWA社チャンピオンシップ・カスタムの仕様が、これに似たものだった、というのが本当のところです。
さて、話は戻ります。
私は、先の3つの部品を組み込んで、ブローバックさせたとき、スライドストップが組み込めるギリギリの長さに調整しています。まず、ゴムリングを1つ、スプリングガイドに入れ、そのあとに、プラ製のカラー、また、ゴムリングという順のあとリコイルSP・リコイルSPガイド、と組み込みました。結果、ショートストロークの効果を、十分に確認できました。私は、その他の軽量化や、ピストンの加工などを、全部一度にやってしまったため、一つ一つの加工の効果を、確認できませんでしたが、現在、全体の銃としてのバランスは、結構良いほうだと思います。そうそう、私は、入手の都合上、プラ製のパイプを使いましたが、シリコンチューブなどのほうが、部品への負担がが少なくなって、良いかもしれませんね。
また、話がそれました。加工の話でした。では、気をとりなおして写真を1枚。

あいや~、見事なピンボケですな。腕の悪さが、窺い知れます。申し訳ない。
この部品は、リコイルプラグです。マルイ純正部品の上半分を、バッサリ切り落としました。あまりやり過ぎると、リコイルSPの保持ができなくなる可能性があります。裏側の写真がありませんが、裏側も、ドリルで肉抜きしてあります。穴が貫通してしまうと、リコイルSPの動きに干渉するかもしれないので、ほどほどにしてあります。
では、もう、一枚。

これまた、ピンボケ。平にご容赦を。純正リコイルSPガイドです。どこか違うのか?といわれるでしょう。ドリルに銜えさせて、耐水ペーパーで磨きました。1000番1500番2000番の順です。その結果、まあ、どうでしょう。ピッカピカになりました。だからどうなの!とツッコミが、入るでしょう。では、ここでオマケの、もう一枚。

ま~た、ピンボケかい!エエ加減にせぃよ!。はい。これが本日最後のピンボケ写真です。
リコイルSPガイドを、正面から撮りました。実は、ガイドを持ったときに、重いなぁ、と思ったのが事の起こりです。じゃあ、穴でも掘ったろ!と思い立ち、万力でガイドを掴み、1ミリのドリルでドリドリしていたとき、掴みが甘く、ガイドが滑って、万力の掴み跡ができてしまいました。仕方がないので、どうせついた傷なので、しっかり掴ませて、しっかりドリドリしました。先の、ピカピカのガイドは、そんな理由からできたものでした。まぁ、結果オーライ!ということにしておきましょう。最悪、失敗しても、傷物にしてしまったスプリンガイドですから、遠慮なく、穴あけできました。
そうそう、今回、なるべく社外パーツは使わずに弄っておりますが、部品調達の都合上、ついでに買った部品がいくつかあります。その都度、載せていきますが、今回のリコイルSPは、PDI社のリコイルSP HDとなっております。これは、狙ったわけではなく、ついでに買ったものです。この製品の、うたい文句の「ソフトなテンションが ガス圧低下による冬場の作動性低下を向上。」というのが、効いているのかは判りませんが、確かに、今の状態では、ノーマルより、燃費がいい様です。
さて、また長くなりました。今回の加工で、リコイルSPガイド・31グラム。リコイルプラグ・13グラム。カラー・ゴム一式・2グラム。リコイルSP・2グラム。計48グラムとなっております。いつものように、ノーマルを量っていないのですが、まさに、爪の垢でしょうね。
以上、リコイルプラグ周辺の加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
2008年11月01日
Hi-Capa5.1④
こんばんは。VUELTAです。
今回は、アウターバレル・インナーバレル周辺・コンペンセイターの加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
では、まず先に、写真を2枚。


はい、もう見慣れたコンプ付のバレル一式です。このコンプは、PDI社製HI-CAPA5.1用SGコンプセットです。
東京マルイ製Hi-Capaシリーズは、ショートリコイルするようになっています。このショートリコイルは、実銃やモデルガンのように、バレル全体がブローバックと共に、ショートリコイルするのではなく、アウターバレルのみが、ショートリコイルするものです。結果、インナーバレルが動かないために、命中精度が良いのだと思います。他の重要な要因は、アフターブローバックとか呼ばれている、BB弾が発射されてから、ブローバックが開始される方式だからとか、いろいろあると思いますが、今回は、バレル周りだけに絞って、話しています。
コンプを外した写真のように、アウターバレルよりインナーバレルのほうが少し長くなっています。写真は、分かり易くするために、アウターバレルを、ショートリコイル位置まで下げています。
さて、なぜ長いかといいますと、コンペンセイターを付けるためのアタッチメントを、取り付けるためです。インナーバレルは、ステンレス製で、05バレルと呼ばれているものです。いずれは、01バレルの7インチを入れるつもりですが、今のところ、腕もなく、大会に参加する予定もないので、このままにしてあります。このままでも、グルーピングに問題はなく、初速も、クローニーで計測して、SⅡS社0.2グラム5.96ミリBB弾で、80m/sほどありますので、必要にして十分の射速があると思います。まぁ、あとあちこち弄っているので、インナーバレルだけのせいではないので、一概には言えませんが…、そのあちこちはそのうち紹介いたします。
少々脱線しましたが、コンプは、インナーバレルにアタッチメントを直接イモネジ3本でネジ止めし、そのカラーにコンプをかぶせ、イモネジ2本で固定する構造になっています。インナーバレル自体がステンレス製で、強度があるからできる技でしょうが、精神衛生的には、あまり良くない構造ですね。実際、コンペンセイターなんて、エアソフトガンには、実用上不必要なものなのでしょうが、そこはそれ、個人的な見栄えや、イメージというものがありますから、良しとしましょう。
で、コンプ周りの写真を2枚。


この写真を見て、おや?と思った方は、このコンプを見慣れている方でしょう。コンプの内壁が、なんかゴチャゴチャして、きれいでないですが、これは下の写真のように、両サイドから穴あけ加工をしたときのドリル跡をそのままにしているせいです。このコンペンセイター、出荷時は、左右の穴のあたりには、凹モールドで、縦長の穴が表現されています。貫通はしていません。これはこれで、十分カッコいいのですが、元ネタのWA社チャンピオンシップ・カスタムは、ウイルソン・スーパーグレードからの流れで好きなモデルなので、ウイルソンのコンプを真似て、両サイドに穴あけ加工をしました。本当は長穴を開けたかったのですが、フライス盤を持っていないので、正確に開ける自信がなかったので、スライド後部の穴に合わせて、8ミリのドリルで左右2箇所計4箇所ドリドリしました。決して軽量化を狙ったわけではないのですが、結果として軽量化につながりました。コンプ単体で、35グラムです。この軽量化というのも、一つ一つは大した重さではないのですが、全体を通してみれば、結構な重さになっているものです。
脱線しました。
本来なら、この後、塗装するのですが、私は塗装が大嫌いなので、ゼブラ・ハイマッキー油性ペンで、塗り塗りしておきました。いずれは、塗装するつもりですが、いつになるやら・・・。
説明が前後しますが、アウターバレル・チャンバー周り・パッキンは、まったくのノーマルです。アウターバレルのパーティングラインすらも、消していません。なぜならば、私は塗装が大嫌い!。パッキンは、磨耗したときに考えます。またそのときに、評判が良い物を試してみましょう。チャンバーは、軽くHOPをかけています。友人たちの話によると、ノンホップより、初速・弾道が安定するとのことなので、それを信用して、ノーマルのまま、ホップをかけて使用します。このバレル周りは、軽量化どころか、ステンレス製のインナーバレルと、軽量とはいえ、アルミ製のコンプアタッチメントを追加していますので、73グラムとなっております。コンプ込みのアッセンブリー重量は、108グラムです。純正の重さは、知りません。計測忘れです。
以上、アウターバレル・インナーバレル周辺・コンペンセイターの加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。
今回は、アウターバレル・インナーバレル周辺・コンペンセイターの加工編にしましょうか。
なお、私の手法を真似して、銃が壊れた、動かない等のクレームは、一切受け付けませんが、コメントなどに、それをやっちゃいかん!とか、こうすれば動くようになる。といったアドバイスを書き込んでいただければ、後の参考になるでしょう。改造は、法律の範囲内で、自己責任において、楽しんで下さい。
では、まず先に、写真を2枚。


はい、もう見慣れたコンプ付のバレル一式です。このコンプは、PDI社製HI-CAPA5.1用SGコンプセットです。
東京マルイ製Hi-Capaシリーズは、ショートリコイルするようになっています。このショートリコイルは、実銃やモデルガンのように、バレル全体がブローバックと共に、ショートリコイルするのではなく、アウターバレルのみが、ショートリコイルするものです。結果、インナーバレルが動かないために、命中精度が良いのだと思います。他の重要な要因は、アフターブローバックとか呼ばれている、BB弾が発射されてから、ブローバックが開始される方式だからとか、いろいろあると思いますが、今回は、バレル周りだけに絞って、話しています。
コンプを外した写真のように、アウターバレルよりインナーバレルのほうが少し長くなっています。写真は、分かり易くするために、アウターバレルを、ショートリコイル位置まで下げています。
さて、なぜ長いかといいますと、コンペンセイターを付けるためのアタッチメントを、取り付けるためです。インナーバレルは、ステンレス製で、05バレルと呼ばれているものです。いずれは、01バレルの7インチを入れるつもりですが、今のところ、腕もなく、大会に参加する予定もないので、このままにしてあります。このままでも、グルーピングに問題はなく、初速も、クローニーで計測して、SⅡS社0.2グラム5.96ミリBB弾で、80m/sほどありますので、必要にして十分の射速があると思います。まぁ、あとあちこち弄っているので、インナーバレルだけのせいではないので、一概には言えませんが…、そのあちこちはそのうち紹介いたします。
少々脱線しましたが、コンプは、インナーバレルにアタッチメントを直接イモネジ3本でネジ止めし、そのカラーにコンプをかぶせ、イモネジ2本で固定する構造になっています。インナーバレル自体がステンレス製で、強度があるからできる技でしょうが、精神衛生的には、あまり良くない構造ですね。実際、コンペンセイターなんて、エアソフトガンには、実用上不必要なものなのでしょうが、そこはそれ、個人的な見栄えや、イメージというものがありますから、良しとしましょう。
で、コンプ周りの写真を2枚。


この写真を見て、おや?と思った方は、このコンプを見慣れている方でしょう。コンプの内壁が、なんかゴチャゴチャして、きれいでないですが、これは下の写真のように、両サイドから穴あけ加工をしたときのドリル跡をそのままにしているせいです。このコンペンセイター、出荷時は、左右の穴のあたりには、凹モールドで、縦長の穴が表現されています。貫通はしていません。これはこれで、十分カッコいいのですが、元ネタのWA社チャンピオンシップ・カスタムは、ウイルソン・スーパーグレードからの流れで好きなモデルなので、ウイルソンのコンプを真似て、両サイドに穴あけ加工をしました。本当は長穴を開けたかったのですが、フライス盤を持っていないので、正確に開ける自信がなかったので、スライド後部の穴に合わせて、8ミリのドリルで左右2箇所計4箇所ドリドリしました。決して軽量化を狙ったわけではないのですが、結果として軽量化につながりました。コンプ単体で、35グラムです。この軽量化というのも、一つ一つは大した重さではないのですが、全体を通してみれば、結構な重さになっているものです。
脱線しました。
本来なら、この後、塗装するのですが、私は塗装が大嫌いなので、ゼブラ・ハイマッキー油性ペンで、塗り塗りしておきました。いずれは、塗装するつもりですが、いつになるやら・・・。
説明が前後しますが、アウターバレル・チャンバー周り・パッキンは、まったくのノーマルです。アウターバレルのパーティングラインすらも、消していません。なぜならば、私は塗装が大嫌い!。パッキンは、磨耗したときに考えます。またそのときに、評判が良い物を試してみましょう。チャンバーは、軽くHOPをかけています。友人たちの話によると、ノンホップより、初速・弾道が安定するとのことなので、それを信用して、ノーマルのまま、ホップをかけて使用します。このバレル周りは、軽量化どころか、ステンレス製のインナーバレルと、軽量とはいえ、アルミ製のコンプアタッチメントを追加していますので、73グラムとなっております。コンプ込みのアッセンブリー重量は、108グラムです。純正の重さは、知りません。計測忘れです。
以上、アウターバレル・インナーバレル周辺・コンペンセイターの加工編でした。
それでは、今日はこの辺で。